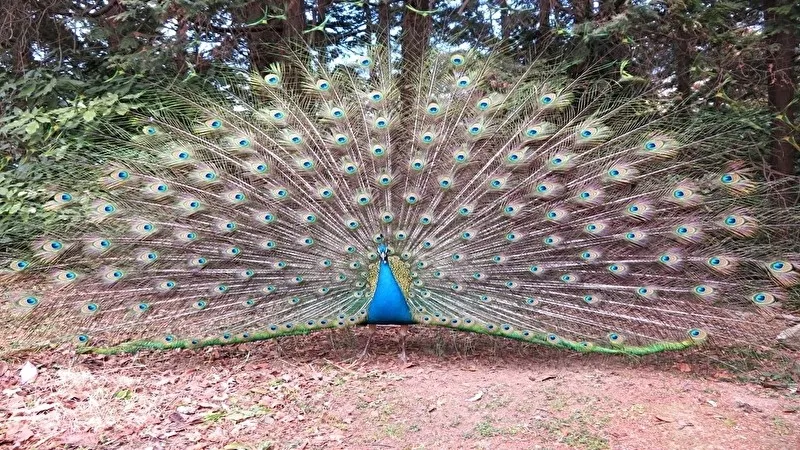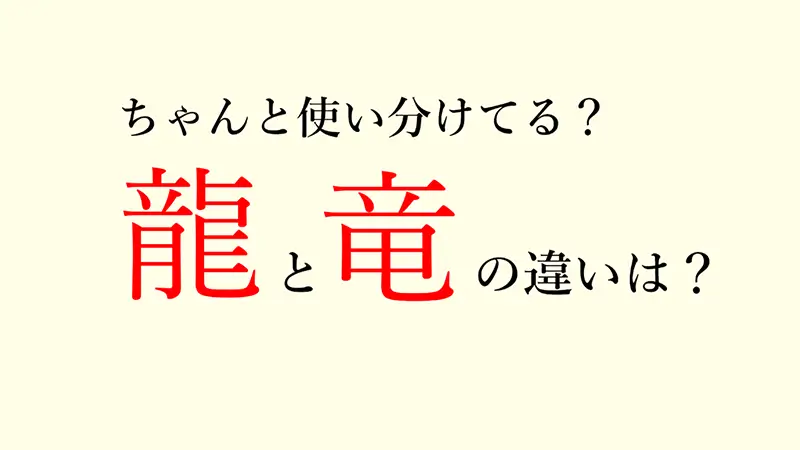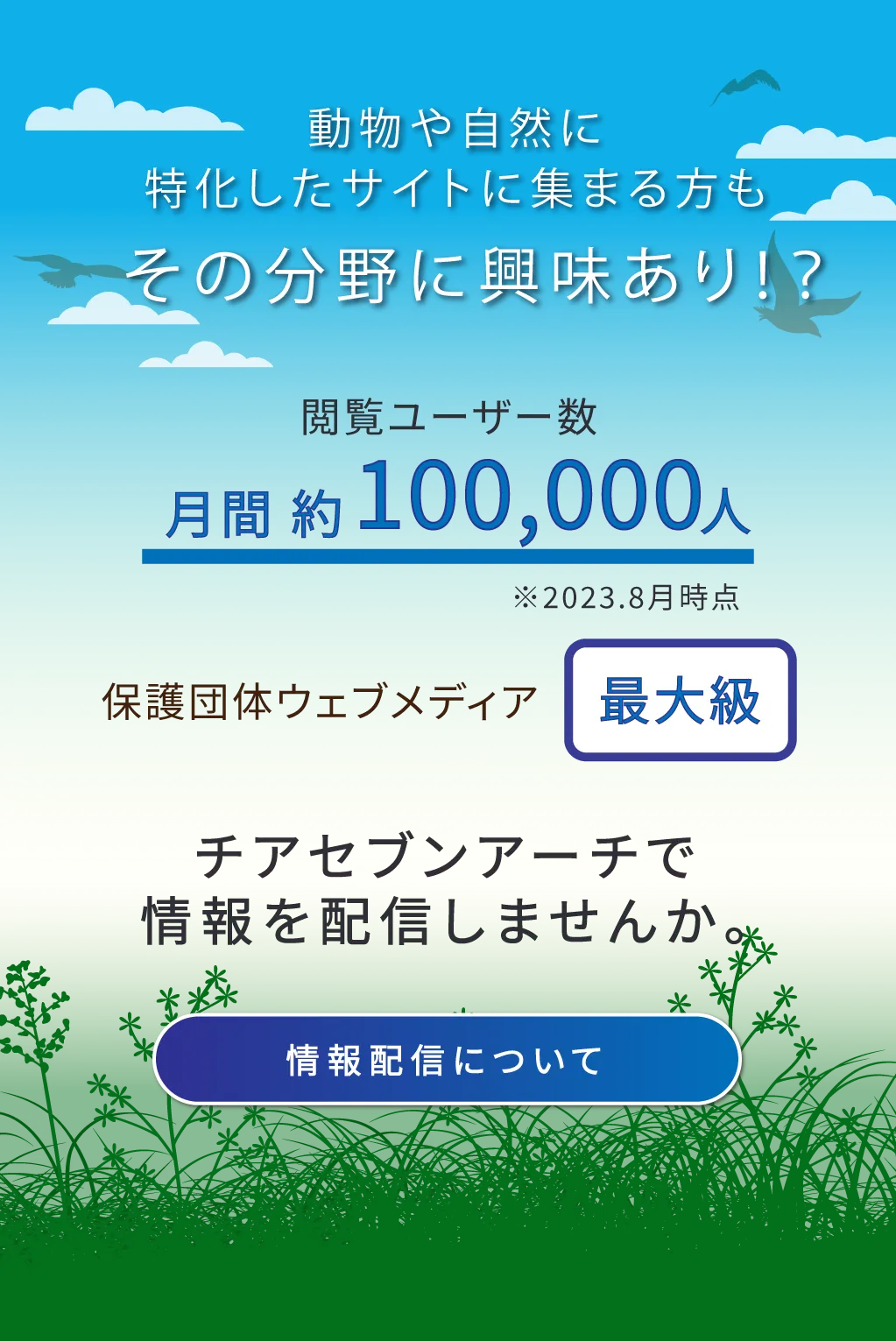渋柿はなぜ干すと甘くなる?自然の仕組みを知ろう
2025.11.6
目次
最近、地元の直売店に行くと渋柿が売られるようになりました。もうそんな時期なんだなと思いながら、そもそもなんで渋柿は干すと甘くなるんだろう?と疑問が浮かびましたので、今回は、渋柿が干すを甘くなる、そんな科学的な理由についてご紹介していきます!
渋柿の渋みの正体は?
実は、渋柿が渋みの正体は、ポリフェノールの一種である、可溶性タンニンと呼ばれるものなんです!
実は柿を乾燥させたりするとタンニンが変化し、渋みを感じにくくすることに繋がってるんです。
引用:Dried Persimmon Fruit: A Year-round Available Product

柿を干すことで渋みが消え、甘みが増す理由
タンニンの変化
干すプロセスでは水分が減ることとともに、可溶性タンニンが酸化・重合・不溶化して、舌に渋みとして感じにくい状態に変わります。例えば、研究では「乾燥によって可溶性タンニンが著しく減少」することが報告されています。
糖分の凝縮
水分が抜けていくことで、果実内部の糖(ブドウ糖や果糖など)が「ぎゅっ」と凝縮され、味が濃くなります。乾燥中に果実表面に白い粉(糖の結晶)として現れることもあります。

太陽と風で作られる、昔ながらの干し柿作り
軒先で天日干しをする手法は、太陽の光や風、夜間の冷気など自然の力を利用して、時間をかけて乾燥させる手法となっています。
柿の内部の水分がゆっくりと抜けることで、当分の凝縮とタンニンの変化が時間をかけて進んでいきます。
特に夜や朝の冷え込みと、乾燥した風がある気候条件の地域では、味の濃い干し柿が出来やすいと言われています。

干し柿にも種類がある
ちなみに山梨県では、枯露柿(ころがき)と呼ばれる干し柿が昔から作られていました。この地域では、渋柿の代表品種である 甲州百目柿 を用いて、皮をむき、燻蒸・吊るし・風に当てて、時間をかけて乾燥させる手法が今なお受け継がれています。
軒先に並ぶ飴色の“柿のカーテン”は、晩秋から冬にかけての山梨の風物詩ともなっています。
まとめ
渋柿を干すことで甘くなるのは、渋み成分タンニンが化学的に変化して渋みを感じなくなり、同時に糖が凝縮して甘みが増すからです。
軒先に吊るされた干し柿には、実はそんな科学的な反応があるんですね。
今年の秋は、その変化のプロセスを少し意識しながら、ゆっくりと干し柿を味わってみませんか?