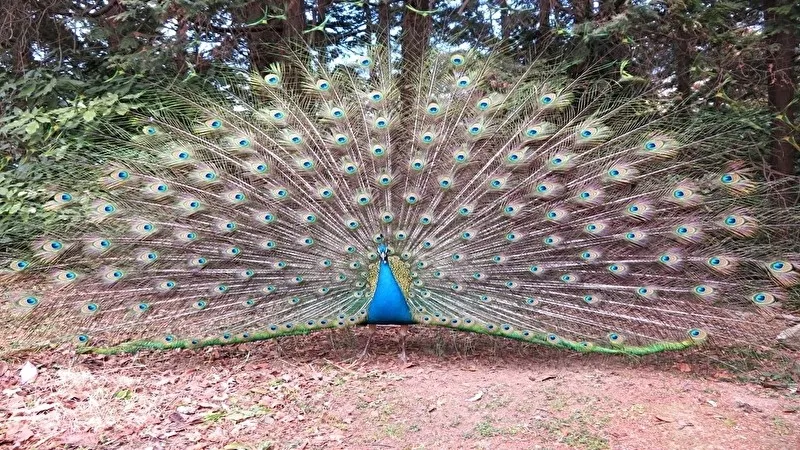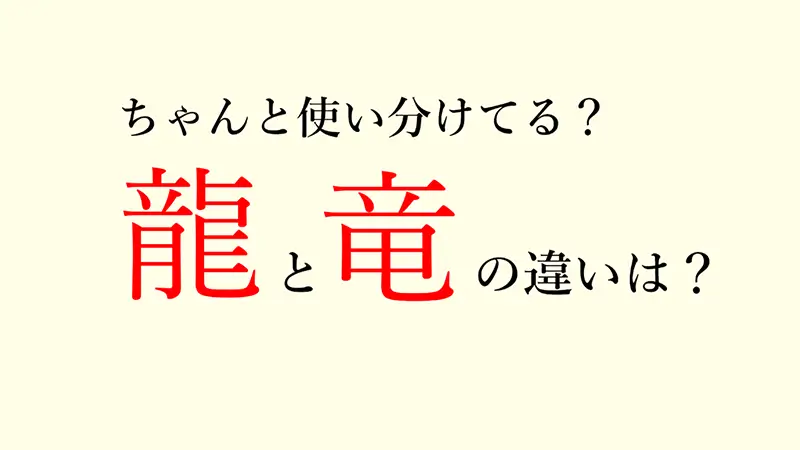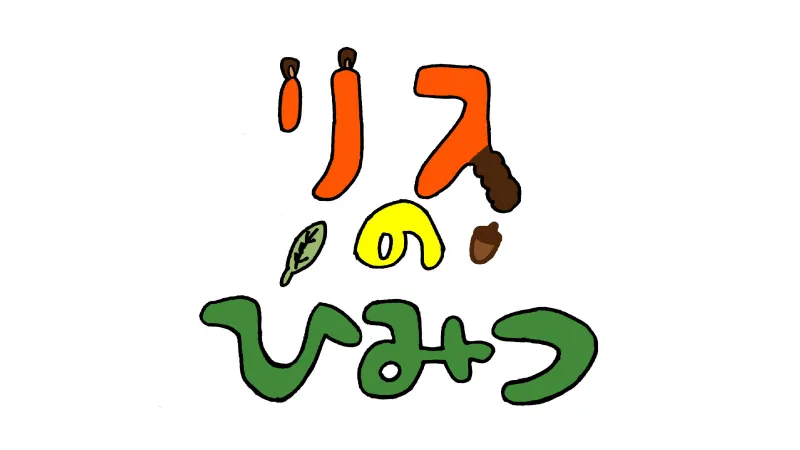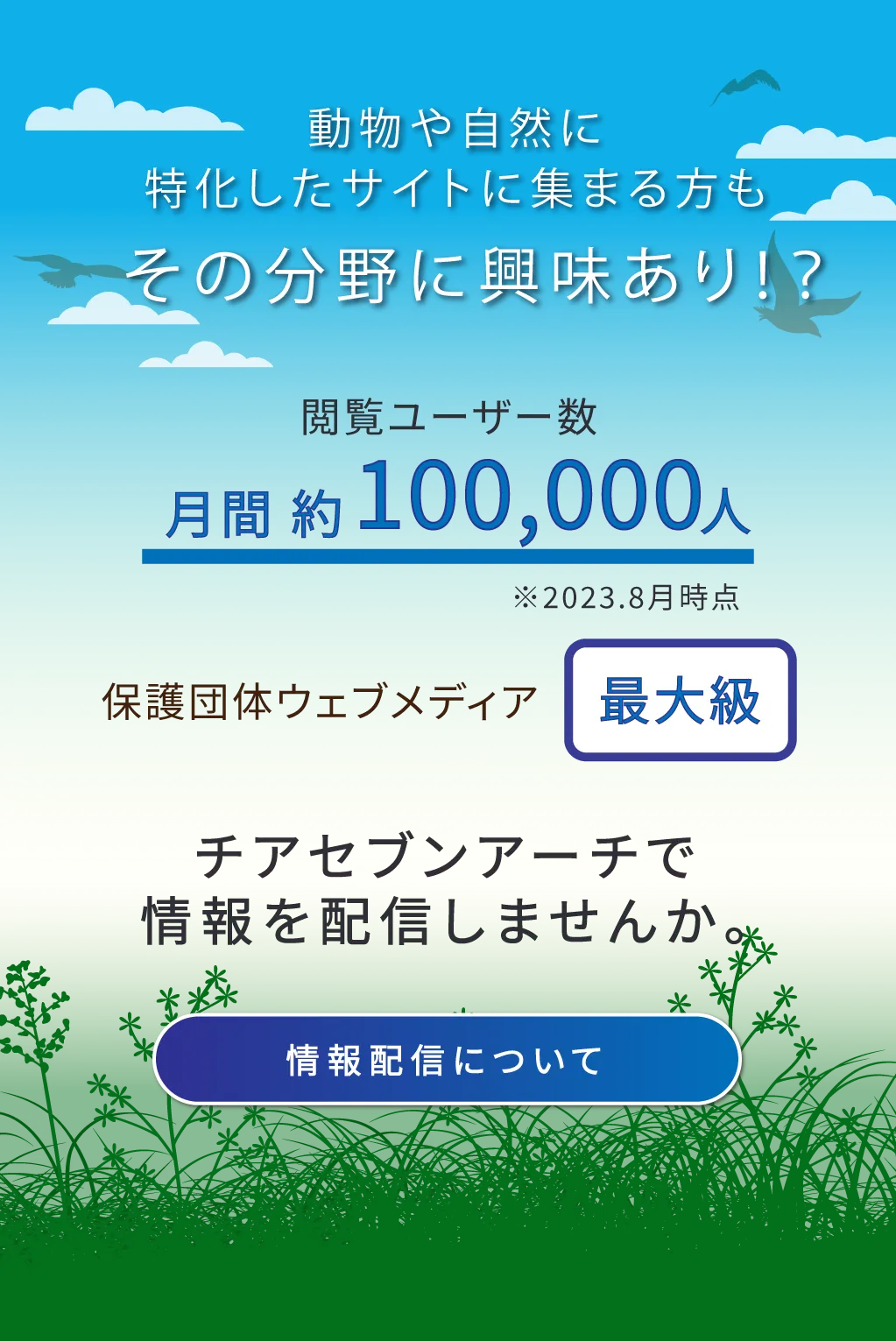サソリの「尻尾」はただの飾りじゃない!毒を操る武器?
2025.8.9
目次
サソリは「サソリ=怖い、生態…?よく知らない」というイメージを持っている人も多いかもしれません。でも、実はその「尻尾」こそがサソリのすごい秘密を握っているんです。
今回はそんなサソリについてご紹介していきます!
サソリの尻尾の特徴は?

サソリの「尻尾」は正式には メタソーマ(metasoma) と呼ばれ、5つの節からできていて、先端には毒をもった テルソン(telson) がついています。
しかもサソリたちは毒を無駄遣いしないように賢く使い分けています。
たとえば「ドライスティング(毒を出さずに刺す)」や「ウェットスティング(毒を注入する)」を状況に応じて選び、エネルギーを節約しながら生き延びているんです。
サソリの毒の仕組みって?

特に有名なデスストーカーサソリの毒には「クロロトキシン」などのたんぱく質が含まれていて、筋肉や神経の働きを強くかき乱す力があります。
たとえば、虫が刺されるとすぐに動けなくなるのはこの毒が原因です。
また、毒に含まれる α-トキシンは、ナトリウムチャネルという神経のスイッチを壊し、体全体がびっくりしてしまうような状態になるんです。
どうしてサソリの尻尾は曲がってるの?

サソリの尻尾がアーチを描いていて、後ろから跳ねかける形をしているのは、獲物を狙ったり、威嚇したりするための工夫です。
種類によって「剣」みたいに素早く試したり、「のこぎり」みたいにゆっくり振ったりするなど、戦い方が全然違うこともわかっているんです。
まとめ
サソリが毒を節約するために、刺す時に毒を注入するかしないか判断してるということは初めて知りました。ただ毒があるイメージのサソリ。色々知っていくと興味深いですね!