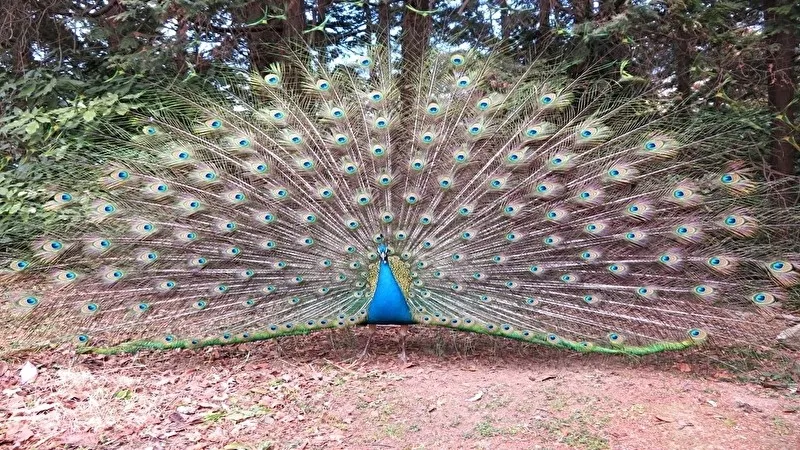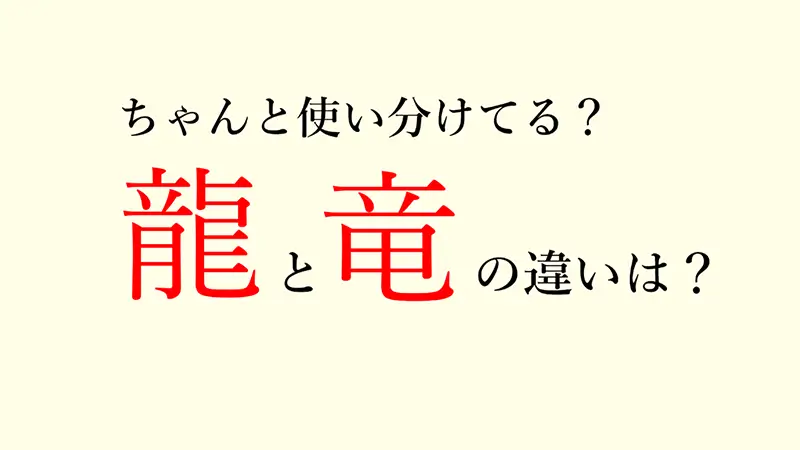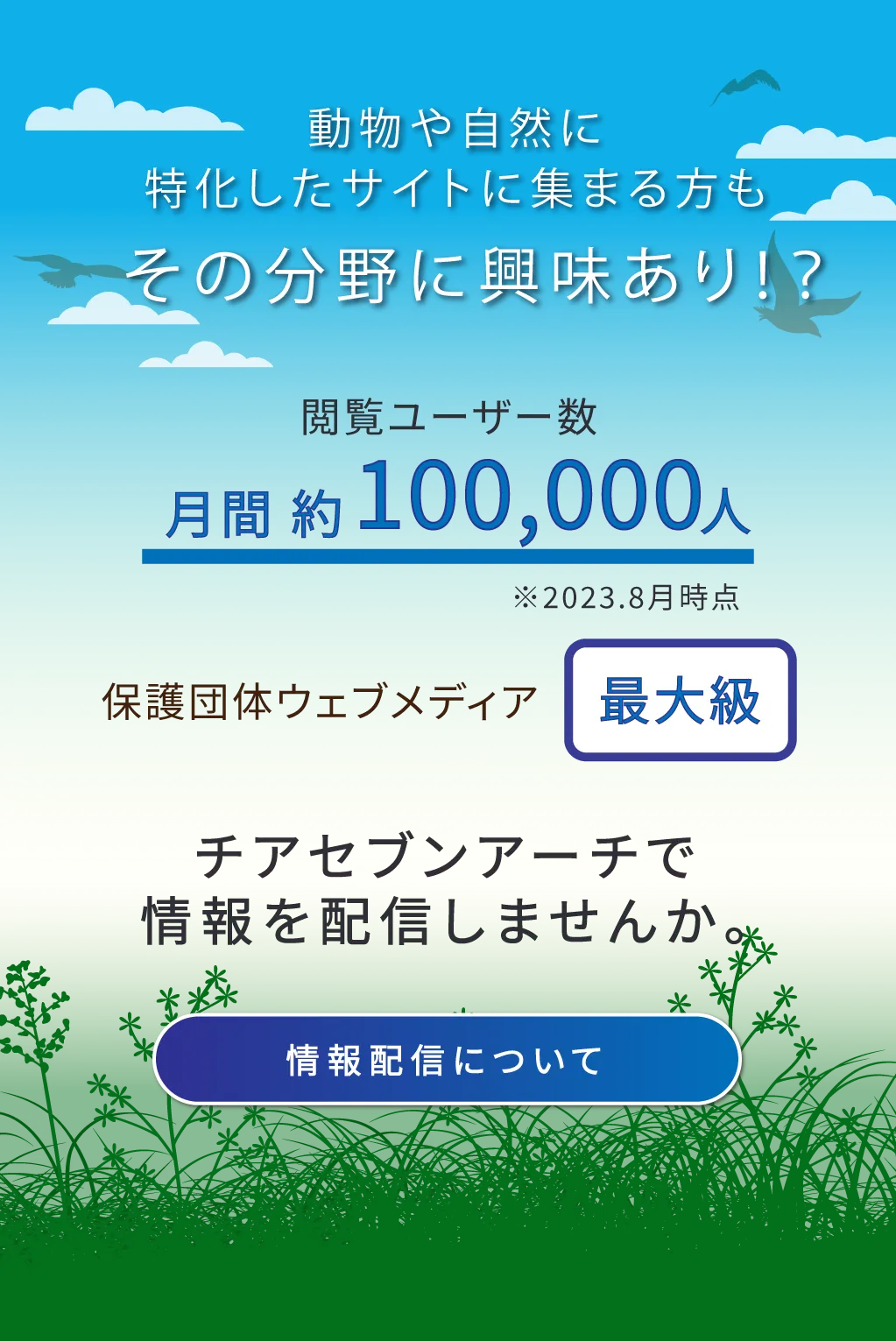カジキとは?カジキマグロと違う?特徴や生態をご紹介
2025.4.16
目次
「カジキ」って聞いたことがありますか?
カジキは水族館でも見られることがなく、生で生きたカジキを見たことがある方は少ないのではと思います。
今回はそのカジキについてご紹介します。
カジキってどんな魚!?
カジキは、海を高速で回遊する大型の魚です。
細長い体と、鋭く突き出た「ツノ」のような上アゴが特徴です。
実はこんなに種類が!
カジキには、メカジキ科かマカジキ科に属します。
日本近海には、主にメカジキ、マカジキ、バショウカジキ、フウライカジキ、シロカジキ、クロカジキの6種が生息しています。

すべて「カジキ科(またはメカジキ科)」に属し、マグロとは分類がまったく異なります。
カジキには他にもいくつか種類が存在し、現在も研究が進んでいます。
カジキの特徴や外観について
体長:およそ1.8〜3.5m(最大で4m以上)
体色:青や金属っぽい銀色
ひれ:背びれが旗のように大きい
上アゴ:硬くて鋭いツノのような上アゴが体長の1/3ほどある
種類や個体によっても差はでますが、一般的に、成体のカジキの体長は約1.8メートルから3.5メートル程度で、最大で4メートル以上になることもあります。
カジキの鮮やかな青い背中には一本のひれが突き出ており、そのひれの形状から「旗魚」と書きます。
また、カジキの体は細長く、体色は青色や金属色を帯びた銀色をしています。
そして、カジキの最大の特徴といっていいツノ。
このツノは上アゴです。
個体差はありますが、一般的には体長の約1/3ほどの長さを持ちます。
この上アゴは、硬い角質でできており、非常に鋭利な先端を持っています。
カジキはこの上アゴを使って、獲物を突き刺したり、敵から身を守ったりすることができます。

カジキの生態や生息域について知ろう
カジキの生態については、高速で泳ぎ、外洋を回遊する大型魚であることが知られています。
カジキは、夏季には温かい海に回遊し、秋から冬にかけては水深の深い場所に移動する傾向があります。
そして、春になるとまた浅い海に沿って回遊するようになります。
水深200mから300m程度の中層を好み、昼間は深海に潜り、夜間に浅瀬に近づくという習性があると言われています。
カジキは主にイカや小魚を食べていますが、サバやカツオなどの大き目の魚も補食します。
カジキは泳ぐスピードが速い(時速60 ~ 100km)ので、獲物を追いかけて捕えることができます。

「カジキマグロ」って実は…
ではよく耳にする「カジキマグロ」って、「カジキなの?」「マグロなの?」って思いますよね。
結論から言うと、カジキマグロという魚は存在しません。
「カジキマグロ」は「カジキ」の総称になります。
つまり、カジキマグロはカジキのことを指しており、マグロではありません。
なんともややこしい名前ですね。
カジキ(カジキマグロ)とマグロの違い
カジキとマグロ、どっちも大きくてかっこいい魚ですが、実はぜんぜん違う種類なんです!どう違うのか、詳しく見てみましょう
カジキ

スズキ目・メカジキ科かマカジキ科
ツノがある
さっぱり系の味
マグロ

スズキ目・サバ科
ツノ無し
部位によって脂がのっている
カジキマグロはカジキの総称になり、メカジキ科かマカジキ科に属します。
マグロはサバ科に属する魚種であり、カジキとは完全に異なる種類の魚です。
分類が違うため、身の食感や味わいも異なると言われています。
しかし、日本ではマグロを獲る方法で一緒にカジキも獲れ、また高級魚としてどちらも扱わられているため、「カジキ」を「カジキマグロ」と呼ぶようになったのかもしれませんね。
海外で実際にカジキを釣り上げた貴重な映像を、ご用意しましたのでぜひご覧ください。
実際に人間と比べると圧巻ですね!
まとめ
今回はカジキについてご紹介しました。
「カジキマグロって名前にマグロとついてるからマグロの仲間かな?」って思いがちですが、カジキの総称ということがお分かりいただけたかと思います。
カジキは生で出会うと人間よりも大きいことがほとんどなので、実際は怖いと思います。
しかし、ダイビングなどで実際に大海原を泳いでるカジキに会ってみたいとも思います。
魚と言えど、大きさや見た目からは、イルカやクジラといった哺乳類と同じくらいのインパクトを受けると思います。