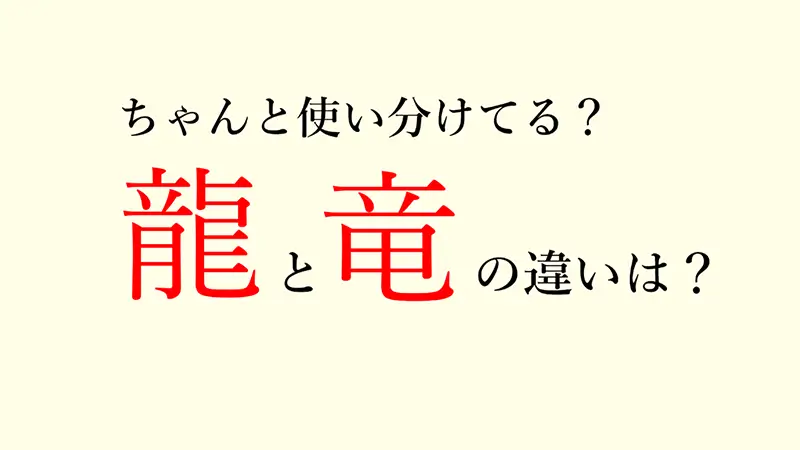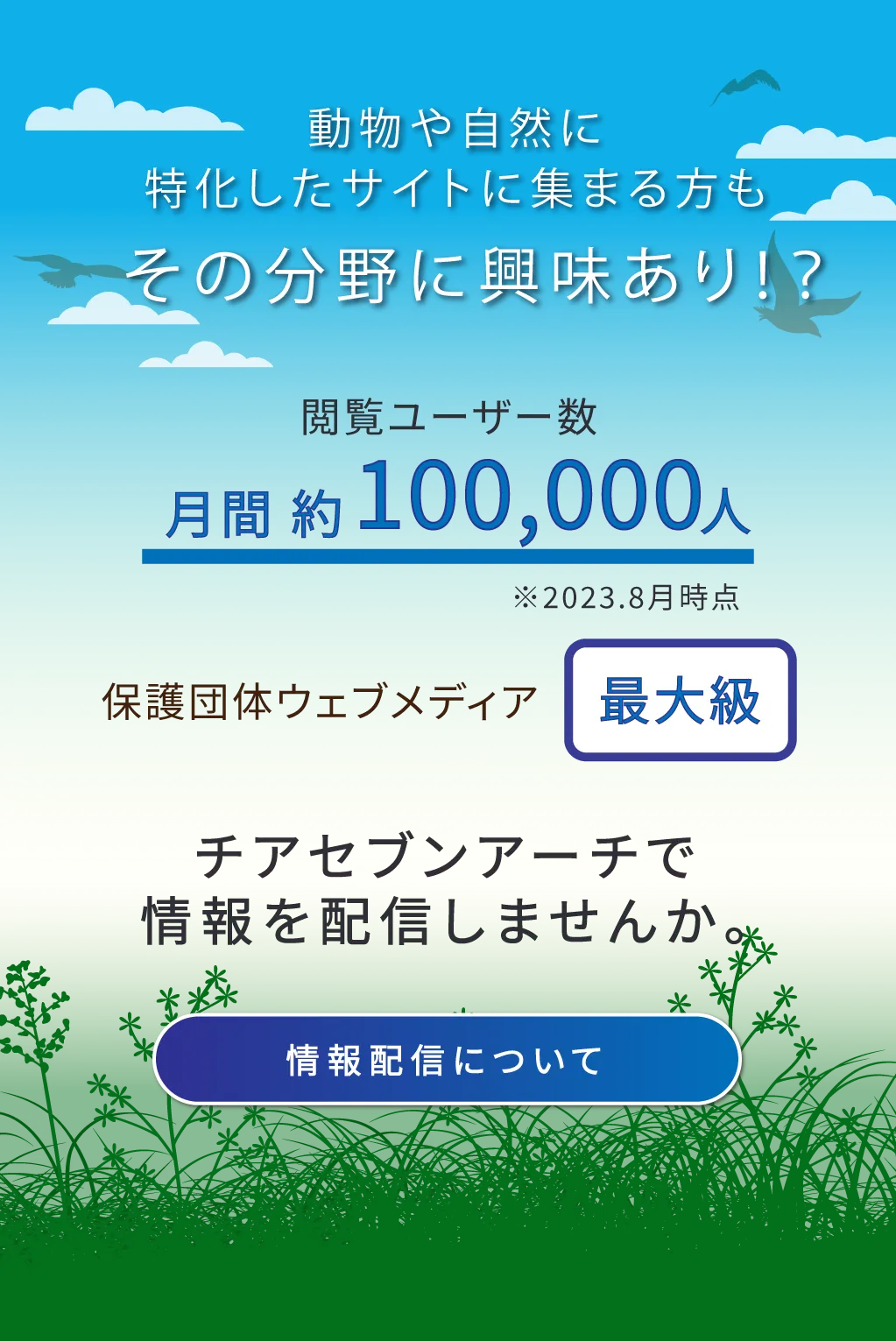疥癬症になるタヌキについて考える。原因は人間にもある!?
2024.4.21
目次
今回は、疥癬(かいせん)になったタヌキについて考えみようと思います。
※アイキャッチ画像含めて、疥癬になったタヌキの画像はNPO法人ジャパンワイルドライフセンターさんからご提供いただいております。
タヌキの疥癬症とは
疥癬とは、ダニの一種である「ヒゼンダニ」が原因で起こる皮膚病の一種です。
疥癬になると、毛が抜け落ち皮膚が見えてしまいます。そして、そのまま衰弱して死亡してしまうことが多いです。
犬猫が食べるドッグフードやキャットフードを野生のタヌキが食べてしまうことが可能性のひとつと考えられています。
犬猫用に作られたドッグフードやキャットフードを野生のタヌキが食べてしまうことが、タヌキにとって過栄養となり、疥癬症を発症・悪化させる要因のひとつの可能性だと考えられています。
例えば、野生のタヌキを見かけた際に良かれと思ってドッグフードやキャットフードを与える方がいます。ただその行動が実は、タヌキを後に苦しめることになっているのです。こうした人間の行動が原因で疥癬になっている場合が考えられます。

ヒゼンダニについて
ヒゼンダニは、ダニ目無気門亜目ヒゼンダニ科に属するダニ。「疥癬」という皮膚感染症を引き起こします。動物だけでなく人間も疥癬はなります。ヒゼンダニは肉眼ではほとんど見えず、メスは角質層にもぐりこんで「疥癬トンネル」という穴を掘り、そこに卵を産み続けます。
※下記の画像はイメージ写真です。実物とは異なります。

疥癬になりやすい野生動物について
タヌキの他にも、キツネ、イタチ、ハクビシン、ウサギなどが挙げられます。
これらの動物は、密集した集団で暮らしていたり、毛皮が密集していたりするため、疥癬が蔓延するリスクが高くなっています。
また、ストレスや栄養不良などが原因で免疫力が低下すると、疥癬にかかりやすくなることが知られています。

タヌキの疥癬を減らす対策について
原因の1つとして考えられる、ドッグフードやキャットフード、その他人間の食べ物を野生のタヌキに与えない。基本的には野生の動物の為、人間から食べ物を与えるのはNGです。
また屋外で犬や猫を飼育し、ドッグフードやキャットフードを外に出しっぱなしにしている場合も注意です。残飯をタヌキが食べることがあります。その為、犬や猫が食べ残したドッグフードやキャットフードは直ぐに片づけることも対策の1つとしてあがります。
好奇心や優しさで動物に食べ物をあげてしまうと、動物は人に慣れてしまいます!
人に慣れた動物は人の食物に手を出すようになり、家や畑に住みつき、別の被害を発生させることがあります。そして害獣駆除の対象になることもある。
ちょっとした好奇心が結果、動物を苦しめることになることがあることを十分に理解する必要がありますね。

疥癬のタヌキを見つけたら、どうしたらいい?
これはお住まいの地域の自治体によって対応が変わります。
主な対応は下記です。
このように保護を検討する自治体もあれば、非介入の自治体もあります。
自治体の地域の環境や人口などが違うので、その地域にあった考え方や対応方法なのだと思います。
その為、疥癬のタヌキを見つけたら、個人で判断せずにまずはお住まいの地域の自治体にご相談しましょう!
まとめ
タヌキの疥癬は元々自然界で発生していたものという議論もございます。
しかし、人間が与えた食べ物によって引き起こされている可能性もある限り、野生のタヌキに好奇心だけで食べ物を与えてはいけないという意識は持つべきものなのかと考えさせられます。