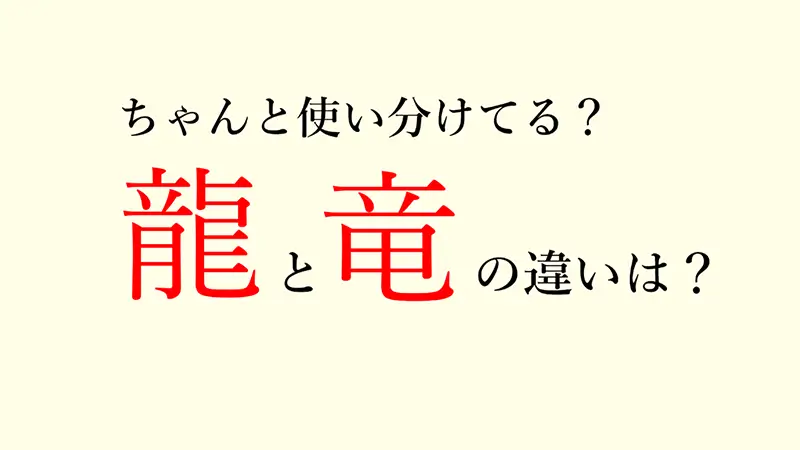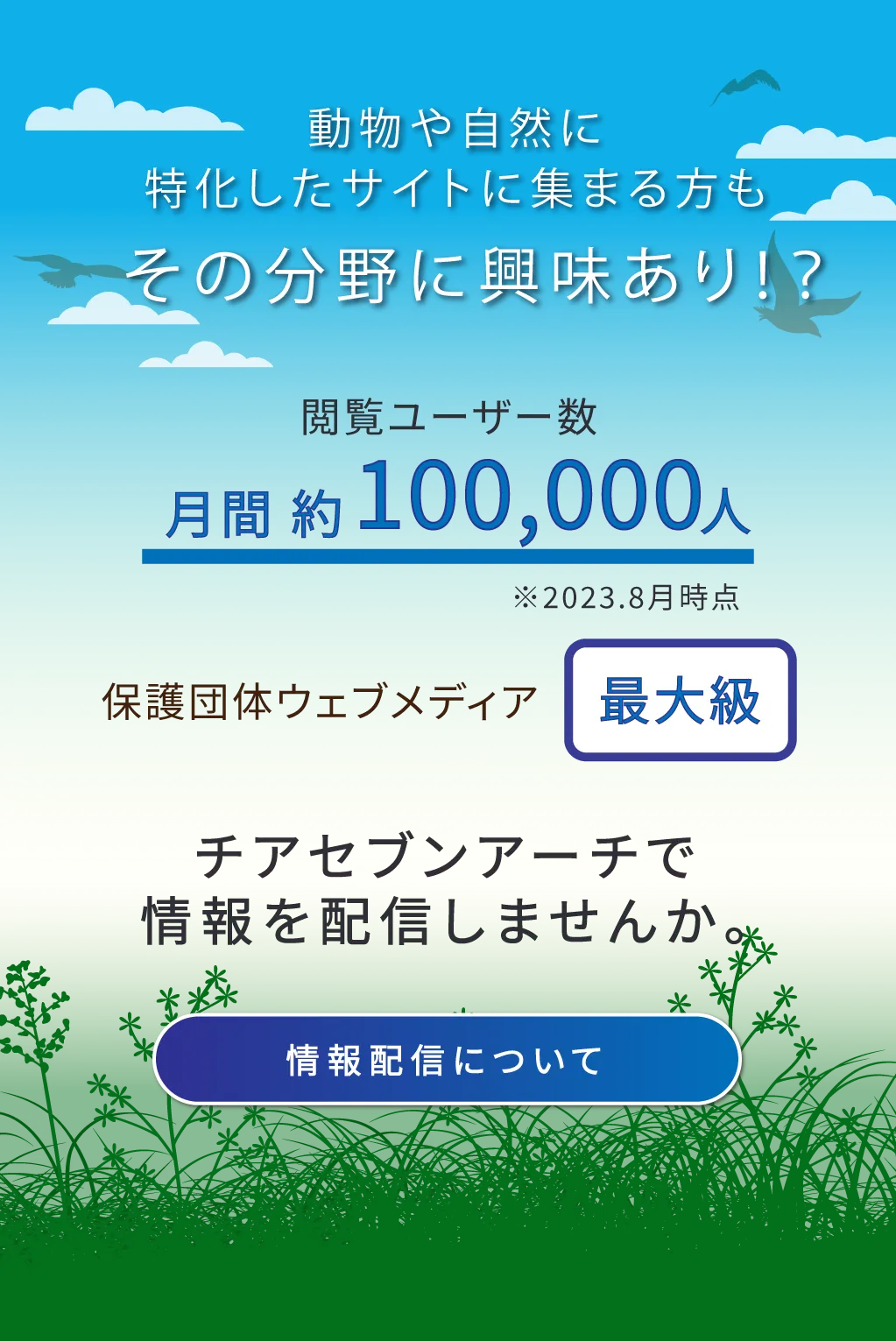カタツムリとナメクジの違いとは?貝はどこから探すの?
2024.4.30
目次
背中に貝を背負った生き物のカタツムリ。いったいどんな生き物なのでしょうか?
でんでんむしむしカタツムリ~。あなたはナメクジとはどう違うの~?あなたの貝殻はどこからいつからあるの~?
カタツムリの特徴や生態とは?
陸上に住んでいるのでわかりにくいのですが、背中に背負っているのは貝。その為、かたつむりは貝の仲間になります!
もっと言うと、砂浜などに生息している巻貝の仲間の中で、海や砂浜ではなく木や植物・岩や石など海から離れた場所に生息しているものをカタツムリと言うとされています。
カタツムリの身体は軟体で、乾燥に弱い生き物です。よく雨上がりなどでかたつむりを見かけるのは、湿気があるからですね!

カタツムリは貝の仲間
前述でカタツムリは巻貝の仲間のうち、より陸上側で生息しているものと紹介しましたが、より詳しく分けると、巻貝はエラ呼吸するのに対してカタツムリは肺呼吸をします。
ここが巻貝とカタツムリの違いかなと思います。
背中の貝はいつからある?どこから手に入れる?
カタツムリは貝の仲間なので、他の貝と同様に生まれた時から貝を背負っています。
そのため、「貝はいつからあるの?」「どこから手に入れるの?」という問いには、生まれた時から親のお腹の中からあるという答えになりますね!
ちなみに、間違えられやすいヤドカリは、生まれた時は貝がありません。自分で成長に応じて、身体にあった貝を探していくスタイルなのがヤドカリ。
カタツムリの貝は成長と共に貝も大きくなっていくので、身体の一部です。ヤドカリとは身体の仕組みが違うのです!

カタツムリとナメクジの違いとは?
カタツムリに似ている生物でヤドカリと同じくらい間違えられるのがナメクジです。
カタツムリとナメクジは、誰が見ても違いは貝の有無だけと言うくらい、貝以外の特徴は同じです。
ただ、それは正しいのです。実はナメクジも貝の仲間です。
ナメクジも貝を背負っていたのですが、退化して貝がだんたんと小さくなっていき見えなくなった種類がナメクジなのです。
つまり、元々は同じ。だから、似ているのですね!
ただ、カタツムリとナメクジでは、人によっては見た時の印象がだいぶ変わると思います。
カタツムリは「可愛い~」、ナメクジは「気持ち悪い~」って印象が多いのはなぜなのだろうか?貝があるか無いかの違いだけで、元は同じなのに…

他にも生物学的分類上で少し違いがあります。生物学的分類においては、カタツムリは柄眼目に、ナメクジは無殻目に分類されます。
カタツムリとナメクジの見分け方は?
カタツムリとナメクジはどちらも軟体動物門腹足鋼(ふくそくこう)に属しており、親戚関係にある生き物です。
しかし、違いもいくつかあります。
一番わかりやすい違いは、もちろん貝殻の有無。また、触角の数も異なります。
カタツムリは4本の触角がありますが、ナメクジは2本の触角があります。
そして、カタツムリとナメクジの住む場所も少し違います。
カタツムリは湿度が高く葉っぱが茂った場所、ナメクジは土管や石の下など地面に近い場所を好む傾向があります。
見た目や生態が似ているカタツムリとナメクジですが、殻や触角の違い、そして食性や住む環境が異なります!
カタツムリは何を食べている?
主に藻や野菜などを食べます。よく、公園や住宅の壁などのコンクリート(石)部分にいる理由は、このコンクリートに付着している藻を食べているからだそうです。

まとめ
今回はカタツムリについてご紹介しました。最近はあまり見ることが無くなったイメージのカタツムリ。
これは、都市開発などでカタツムリの住みやすい環境が減少してきたからだと言われています。
それでも、雨上がりのタイミングなどでは公園の草むらなどでは見かけることもあります。
見た目は軟体動物なので、くねくねして気持ち悪がられがちですが、貝の仲間だと思ってみればどうですか?少し、見る目が変わるのでは無いでしょうか。