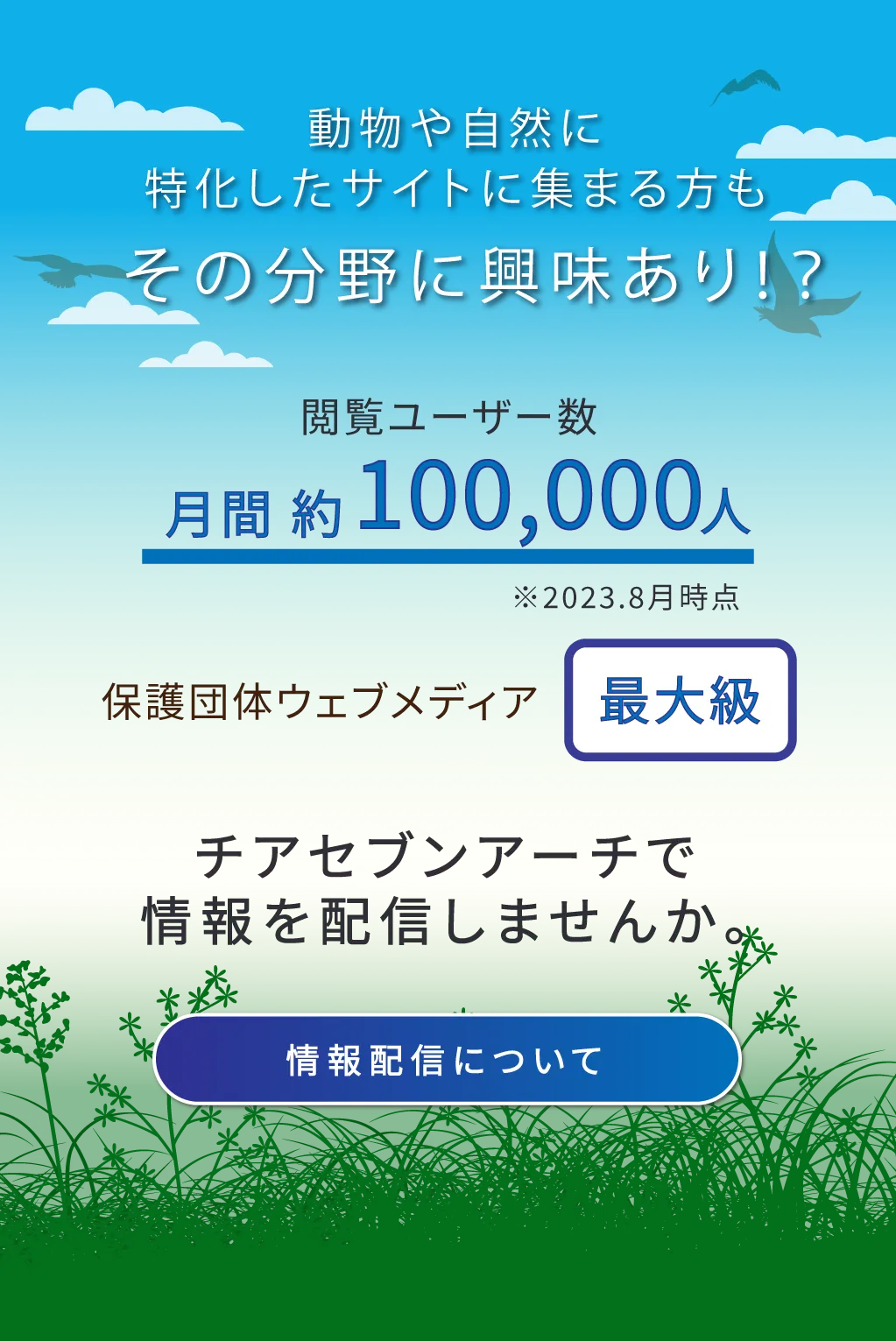アライグマの特徴や生態をご紹介。なぜ害獣になっているか。
2025.7.3
目次
今回はほぼ日本全国に分布し野生で繫殖もしているアライグマについてご紹介します。
アライグマは可愛らしい見た目とは裏腹に、実は非常に厄介な「害獣」として扱われています。
なぜアライグマが害獣とされるのか見てみましょう。
アライグマの特徴や生態を知ろう!
・哺乳綱食肉目アライグマ科アライグマ属
・体長は40 ~ 70cmくらい
・夜行性
・特定外来生物
アライグマは哺乳綱食肉目アライグマ科に属する動物で、体長はおよそ40〜70cmほど。夜行性で、主に夜間に活動する習性を持っています。
アライグマ属なのでタヌキやキツネとは違うのだが、外見が似ている為良く間違われます。
アライグマとタヌキの見分け方の特徴としては尻尾にある縞模様の有無です。
特にタヌキと間違われるので、この尻尾の違いは分かりやすいポイント。
タヌキ

アライグマ

他の見分け方としてタヌキは犬や猫と同じで爪先で歩くのに対して、アライグマはかかとまで足がつくんだそうです。
人間の生活圏に適応しやすく、ゴミ捨て場などが餌場になりやすいのです。
アライグマは、繁殖力が強く、個体数が急激に増える要因となっています。

前足で器用にドアノブを回したり、ゴミ箱のふたを開けたりすることも可能なんだそうです。
また、一度学習したことを覚える記憶力も高く、罠を避けることもあります。
個体差はありますが、1〜3kmほどの範囲を移動して活動すると言われ、巣と餌場を覚えて繰り返し通う習性があります。
日本には1970年代以降、ペット目的で輸入されたのが始まりです。飼いきれずに捨てられた個体が野生化し、今では全国に分布しています。現在は「特定外来生物」に指定され、飼育や放獣は禁止されています。
出典元:摂津市ホームページ
名前の由来
実際には洗っているわけではなく、触覚で食べ物などを確認している仕草と言われています。

アライグマは害獣扱い?!
アライグマは特定外来生物として扱われ、雑食性で農作物や小型生物を幅広く捕食します。日本には天敵が少ないため繁殖が拡大し、農産物への被害や生態系への悪影響が懸念されています。
出典元:アライグマ防除の手引き (環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室)
凶暴な性格と人への攻撃性
アライグマは野生動物であり、追い詰められると鋭い爪や歯で攻撃してくることがあります。特に子どもを連れているメスは非常に攻撃的です。

住宅への侵入と被害(屋根裏・壁内など)
屋根の隙間や換気口から侵入し、天井裏や壁内に巣を作ります。糞尿や巣材によって家屋の損傷・悪臭被害が起こることもあるんだそうです。
糞尿による悪臭・汚染リスク
糞尿は強い臭気を放つだけでなく、ウイルスやカビ、細菌の温床となり、室内環境を汚染する原因になります。
病原菌・寄生虫の媒介
アライグマは狂犬病ウイルスやアライグマ回虫といった病原体を保有していることがあり、人への健康被害を引き起こす恐れがあるそうです。
野生のアライグマに会ったら?!
すでに日本のほぼ全国へと生息地が拡大しているアライグマ。
河川敷や山など、自然豊かな場所で主に野生のアライグマを見かけます。
そういった自然豊かな場所で目撃した場合は、まずは近寄らない・餌を与えないといった意識が大事です。
追い詰めたり・脅かしたりと刺激を与えると、人間に危害を加える可能性もあります。
そっとその場を離れてください。

地域によって対応が変わります。
ただし、基本的にはアライグマは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、許可なく捕獲することが禁止されています。
そのため、個人の判断で対応するのは注意が必要です。
アライグマ対策をしっかりしよう!
屋根や基礎の隙間の封鎖
アライグマは小さな穴からも侵入できるため、5cm以上の隙間は金網や板でしっかり塞ぎましょう。
ゴミ箱のふたをしっかり閉める
アライグマは蓋の空いたゴミ箱を狙うため、ふた付き・ロック付きのゴミ箱が有効だそうです。
忌避剤やセンサーライトの活用
市販の忌避スプレーやセンサーライト、音波装置なども効果的です。ただし、持続的な効果には限界があるようです。
プロの駆除業者に依頼
自分での完全対策は困難なため、もし、アライグマが家に入りこんでしまう時にはプロに相談・依頼することで根本的な解決だそうです。

引用元:ORKIN CANADA
引用元:WORLD CLASS WILDLIFE REMOVAL
まとめ
日本では元々いないとされているアライグマ。人間が輸入し、それがきっかけで野生化し繫殖。
そして特定外来生物として害獣となり、駆除の対象にもなる。
農業をされている方や、地域によってアライグマの被害を受けている方がたくさんいる為、駆除の対象になるのは仕方の無いことかもしれません。
これは外来種だけではなく在来種にも言えることですが、人間と野生の動物が同じ地で生きている以上、何らかの形での接触は発生します。
その地域や環境ごとで駆除の対象・保護の対象という考え方が分かれるのも理解はできます。
共存とは理想ばかりですが、少しでも人間と野生の動物両方にとって、良い環境になるように取り組みをしていかないといけないですね。
そして、在来種だけでもそのような問題は多々ありますので、アライグマのような外来種で問題数をさらに増加させないように意識も必要です。